各事業所や、工場内にISO9001やISO/IATF16949の内部監査員が何人かいるかと思います。
しかし、内部監査員という者は異動、定年退職などのいろんな要因で毎年必ず減っていきます。なので定期的に補充をしなければどんどん人数が減っていき内部監査を行うにも支障が出てくるようになります。
では、新しい内部監査員を増やす、新規登録するには、どのような教育や研修が必要なのでしょうか。何か外部機関で、研修を受けさせにいく必要があるのでしょうか?
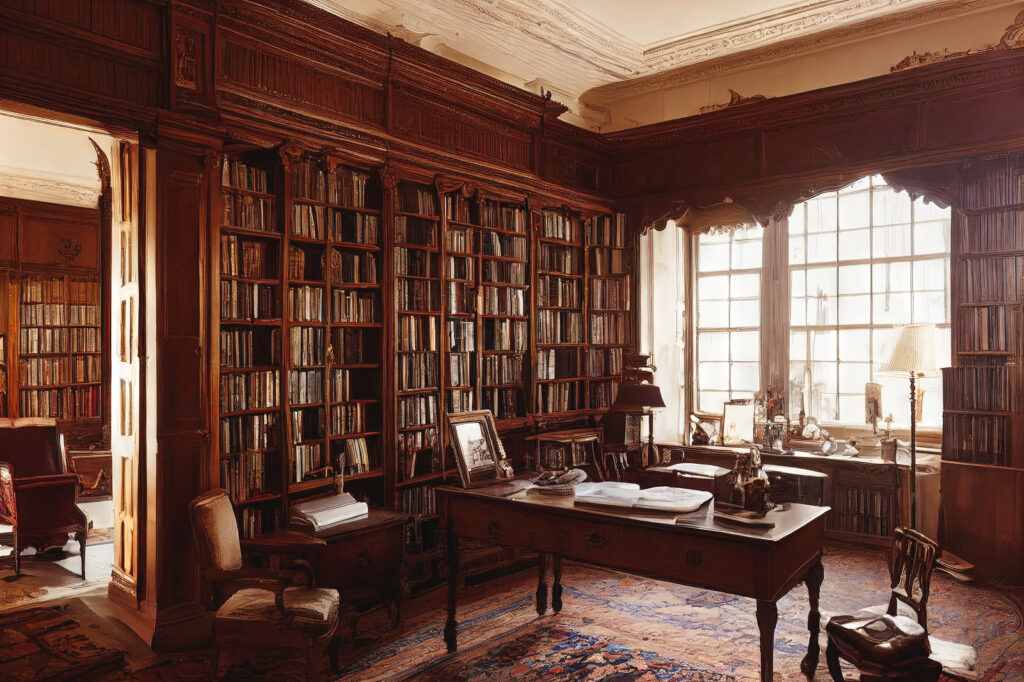
答えは、外部の研修機関に受けさせに行ってもいいですし、工場など事業所の中で、教育をして登録しても構いません。まず外部研修に受けに行く場合は通常の内部監査員育成コースですと1泊2日のメニューになります。
私も東京にある、民間企業で行われていた研修コースに参加しました。1日目が座学、2日目が演習だったと思います。簡単なテストもありますが、受けらせるための確認テストなので、落ちる心配はありません。
2日目の終わりに、終了証をもらえます。メリットとしては、外部委託の教育なので社内で研修の準備をしなくていいのとプロの講師による研修ですのでより深い知識習得が可能となります。
デメリットとしては、1度に少人数しか送り込めないことまた毎月行っているわけではなく年間の研修コースも限られていますので1年に2~3人新規に増やすことができればいいほうでしょう。
料金も、受講費用だけで4万近くします。では、社内たとえば、工場内で教育をするとしたら、どうしたらいいでしょうか?テキストなどのメニューは?確認テストは?
などいろいろわからない点はあるかと思います。私のケースでは、本社のISO推進室がパワーポイントの教育用の資料を持っておりましたのでそれを用いて行い、確認テストも過去作ったものがありましたので、自分で少しだけアレンジして作ってみました。
では研修の時間は?座学1時間半程度、確認テストは30分程度50問くらいの択一式のテストを行いました。7割以上が合格です。
講師は私が行いました。広めの会議室に30人くらい集めて、パワーポイントで説明を行いました。研修テキスト内容のレジュメは主に下記の通りです。
ISO9001とは何か?
ISO、社内規格、現場の作業標準書に至るまでの簡単な体系図
内部監査PDCAの流れ
指摘の仕方、監査調書の書き方
MI-NCやOFIの違い
コアツールの説明
APQPなどコアツールは5つありますが、それぞれパワーポイント1枚~2枚くらいで説明し、それだけだとイメージがつかないので実際に社内で普段用いている、帳票や記録類を実際に提示してやり方を説明しました。
これらを合わせると40ページくらいのボリュームなので、要点を絞ってテンポよく説明することが重要です。では100個以上ある、ISOの要求事項はどのように教育すればいいのでしょうか?1個1個説明すると日が暮れそうですね。僕は資料だけ渡して、自己学習ということにしました。
ISOの概要説明やコアツールの説明においては、中には、本社のISO推進室が作った音声ナレーション付きのパワーポイントの説明資料をスライドで映して、音声を流すだけという手法を用いているところもあるみたいですがそれは、絶対にやめたほうがいいです。
製造現場からは大不評だったらしいです。工場内での内部監査員研修にそれを用いたらしいですが、現場の人たちにとっては、何を言っているのか、さっぱりわからないとのことでした。製造課の主任や班長レベルの方も内部監査員研修を受ける機会が多いと思いますが、多くの方は高卒です。
なので、難しい用語など使うとまず理解してくれませんしその瞬間、研修が無意味になります。更に悪いことには本社のISO推進室にいる人は、現場経験工場で勤務した経験がなく机上のこと、一般論でしか言えないので、実際の現場のオペレーションとはそぐわないことを言っており、役に立たないケースもあります。なので、私は自分で講師をしました。
極力、現場の人にも分かる言葉を使い難しい専門用語も、例えばこうの用語はこういうことを言っているんですという補足説明をします。そして普段の現場のやり方に置き換えて、具体的に説明するようにしました。
実際の現場で使用している帳票とかを用いて説明したりするといいかと思います。そして、内部監査のやり方においては具体的にこれとこれをすればいいいというように、的確に説明をするようにします。
そして確認テストを行い、不合格だった人には、少しだけ問題を変えて追試をさせて合格してもらい工場内にて賞状みたいな終了証を作って渡して、内部監査員の登録リストを作成し課長のハンコをもらって保管すればOKです。これをやることで、1回の研修プログラムにて一気に30人くらい内部監査員を増やすことも可能です。
もちろん内部監査員研修の講師を社内でする場合は、その人は内部監査員である必要があり(そうしないと本審査の力量評価にて説明がつかない)自らしっかり語って説明できるように関連の専門書を読破して普段の事業所内の業務に置き換えたらここはこう対応すればいいというのを語れるレベルになる必要があります。



コメント